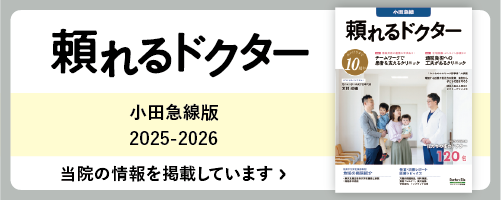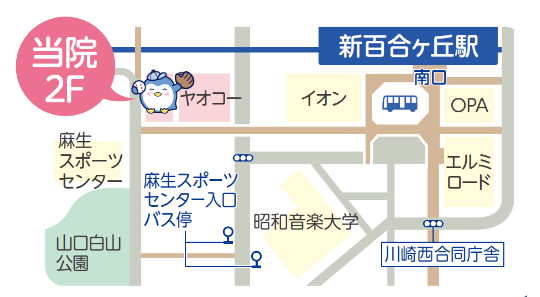私たちの身の回りには、細菌やウイルスによって引き起こされる様々な感染症があります。
予防接種は病気に感染するリスクを減らし、感染した場合でも重症化を防ぐ効果があります。
一度かかってしまうと重篤な後遺症を残してしまうものや命に係わる感染症もあります。
お子さまを重篤な病気から守るために、適切な時期に必要な予防接種を済ませておきましょう。
予防接種の種類とそれぞれのワクチンについて
- 定期接種(公費)
-
- ヒブ
- 肺炎球菌
- 四種混合
- 五種混合(四種混合+ヒブ)
- ロタ
- BCG
- 麻疹・風疹(MR)
- 水痘(水ぼうそう)
- 日本脳炎
- 二種混合(DT)
- 子宮頸がん
- 任意接種(自費)
-
- ムンプス
- インフルエンザ
- 三種混合
- 不活化ポリオ
予防接種スケジュールについて
予防接種は生後2か月(ロタワクチンは生後6週)から接種が可能です。
以前はワクチン同士の接種間隔を一定期間あける必要がありましたが、2020年10月から注射の生ワクチンを連続して接種する場合のみ、4週間(中27日)あけることに変更されました。
0歳台の予防接種は種類も多く、体調を崩して予定通り接種が進まない場合もあります。
スケジュールについてお困りの際はご相談ください。
予防接種の予約について
当院では2か月前から予防接種の予約が可能です。
診療時間内は感染対策のため専用待合室へご案内いたします。
また14時~15時までは予防接種・乳児健診専用の時間帯となっておりますので感染症が気になる方はこちらをご利用ください。
当日の持ち物
- 母子手帳
- 予防接種予診票 ※来院前にご記載してからお持ちください。
- 健康保険証
- 医療証又はマイナンバーカード
注意事項
- 予防接種予診票は事前にご記入してからお持ちください。
- 接種前に診察をさせていただきますので、脱がせやすい恰好でご来院ください。
- 接種時に嘔吐してしまう可能性があるため、予約時間の30分前から授乳はお控えください。
- 接種後の入浴は問題ありませんが、激しい運動は控えましょう。
- 副反応など予防接種についてご不安なことがございましたら、何でもご相談ください。
ワクチンについて
Hibワクチン
Hib(ヒブ)とはインフルエンザ桿菌B型という細菌のことで、毎年冬になると流行するインフルエンザウイルスとは異なります。
Hibによる重篤な感染症に細菌性髄膜炎があります。
細菌性髄膜炎にかかってしまった子どもの約70%が0~1歳児で、集団生活をされているお子さまやご兄弟がいるお子さまはよりかかりやすいと言われています。
一度かかってしまうと後遺症を残してしまうことも多く、命にかかわる場合もありますので、生後2か月になったらすぐに初回接種を開始しましょう。
2024年2月以降に生まれた赤ちゃんは4種混合にヒブを追加した5種混合ワクチンの接種が開始されました。
接種可能年齢
生後2か月以上5歳未満
接種回数
27日から56日の間隔をあけて3回
初回接種(3回目)終了後7か月以上あけて、1歳以降に1回
※初回接種を開始した月齢により接種回数が異なりますので、接種が遅れてしまった際は一度ご相談ください。
肺炎球菌ワクチン
肺炎球菌は鼻やのどに住みついて肺炎、中耳炎をひき起こす細菌で、まれに重篤な細菌性髄膜炎や菌血症をひき起こします。
肺炎球菌による細菌性髄膜炎はHibよりも重症度が高く、約30~40%の方に後遺症がみられ、約10%の方が亡くなると言われています。
集団生活をされているお子さまやご兄弟がいるお子さまはよりかかりやすいと言われていますので、生後2か月になったらすぐに初回接種を開始しましょう。
肺炎球菌には多くの型が存在し、これまで13価ワクチンが使用されてきましたが、2024年4月から15価、10月から20価のワクチンが使用可能となりました。
接種可能年齢
生後2か月以上5歳未満
接種回数
27日の間隔をあけて1歳までに3回
初回接種(3回目)終了後60日以上あけて、1歳から1歳3か月までに1回
※初回接種を開始した月齢により接種回数が異なります。接種が遅れてしまった際は一度ご相談ください。
五種混合ワクチン
五種混合ワクチンとはジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ、インフルエンザ桿菌B型の5種類の病気を予防するワクチンです。
2024年4月から四種混合ワクチンにヒブワクチンが追加された五種混合ワクチンが導入されました。
注射の回数が減り、お子さまが痛い思いをすることを減らすことができますが、これまで使用されていた四種混合ワクチン、ヒブワクチンとの互換性が明らかではないため、原則として四種混合+Hibの形で開始されたお子さまは五種混合ワクチンに変更できず、四種混合+Hibの形で継続することになります。
接種可能年齢
生後2か月以上7歳6か月未満
接種回数
20日から56日の間隔をあけて3回
初回接種(3回目)終了後、6か月~18か月あけて、かつ生後12か月以降に1回
ロタウイルスワクチン
胃腸炎の原因になるウイルスはたくさんありますが、ロタウイルスは感染力も強く、嘔吐や下痢が重篤化しやすいため、点滴での治療や入院が必要となることが多いウイルスです。
また脱水だけでなく、繰り返す痙攣、脳症の原因となることがあります。
ロタウイルスは多くの種類(型)があり、5歳までに少なくとも1回以上はかかります。
2回以上かかると重症化する可能性は低くなるため、ワクチンを接種することにより1回目の感染から症状を軽くすることができます。
ロタウイルスワクチンには1つの型を含むロタリックス(2回接種)と5つの型を含むロタテック(3回接種)があり、いずれも生後6週から接種が可能ですが14週6日までに初回接種を行う必要があります。
2種類のワクチンで予防効果に差はないと言われておりますが、途中でワクチンを変更することはできません。
ロタリックス
接種可能年齢
生後6週から24週
接種回数
27日以上あけて2回
ロタテック
接種可能年齢
生後6週から32週
接種回数
27日以上あけて3回
※どちらも内服のワクチンになります。
BCG
BCGは結核を予防するワクチンです。
結核と聞くと昔の病気というイメージがあるかもしれませんが、毎年約20000人の方が発症しております。
乳幼児期に結核菌に感染してしまうと粟粒結核という重症な肺炎や髄膜炎となり、後遺症を残したり命にかかわることがあるため日本ではBCG接種が続けられています。
接種2~3週間後に少しずつ赤く腫れたり、膿が出ることがありますが、数か月で自然によくなります。
接種後すぐに針跡が腫れたり、膿がでてきたりする場合(コッホ現象)は、接種前から結核に感染していた可能性があります。
必要な場合は検査を行うことがあるため早めにご相談ください。
接種可能年齢
1歳未満
接種回数
1回 スタンプ式の接種
※接種後は接種部位が乾くまで院内でお待ちいただきます。
MR(麻疹・風疹)ワクチン
MRワクチンは麻疹と風疹の感染を防ぐワクチンです。
麻疹は非常に感染力が強く(空気感染)、肺炎や脳炎といった重症化することがあります。
また麻疹にかかってから数年後に亜急性硬化性全脳炎(SSPE)といった難病を発症することがありますが根本的な治療はありません。
風疹も麻疹ほどではないですが感染力の強いウイルスです。
熱や発疹、首の後ろのリンパ節腫脹など軽い症状で治まることが多いですが、時に脳症を起こすことがあります。
また妊娠初期の妊婦が風疹に感染してしまうと、お腹の中の赤ちゃんが先天性風疹症候群になってしまうことがあるため、保護者の方の予防も重要になります。
妊娠中に抗体価の低下を指摘されたり、今後妊娠を希望されている方は一度ご相談ください。
接種可能年齢
1期:1歳以上2歳未満
2期:5歳以上7歳未満(就学前の1年間)
※地域で流行している場合、生後6か月から接種が可能です。(自費接種)
水痘(水ぼうそう)ワクチン
水痘は水痘帯状疱疹ウイルスの感染により全身に発疹が出現する病気で、麻疹と同様に空気感染するため非常に感染力が強いウイルスです。
発疹ができるだけと思われがちですが、稀に脳炎や肺炎、脳梗塞などを重篤な合併症を引き起こすことがあります。
また、1度感染してしまうと神経細胞に残り、免疫力が落ちた時などに帯状疱疹として発症することがあります。
接種可能年齢
1歳以上3歳未満
接種回数
1歳以上で1回
1回目終了後から3~6か月あけて1回
日本脳炎ワクチン
日本脳炎ウイルスに感染した豚の血液を吸った蚊を介して人に感染するウイルスです。
感染した人がすべて発症するわけではなく、多くの人は症状がみられません。
しかし約100~1000人に1人が脳炎を発症し、そのうち15%の方が亡くなると言われています。
これまで患者は西日本に多いと言われていましたが、最近では関東地方の豚も日本脳炎に感染していると言われています。
以前は日本脳炎ワクチン接種後に脳炎の一種の亜急性散在性脳脊髄炎(ADEM)の重症例が起こったため接種が一時見合わせ(積極的推奨の差し控え)となりました。
現在は特例措置が取られ、接種見合わせの間の不足回数分を定期接種として受けられます。
接種可能年齢
1期:生後6か月から7歳6か月未満
2期:9歳以上13歳未満
接種回数
1期:1~4週間隔で2回 2回目の接種の約1年後に3回目
2期:9~12歳に1回
※標準的には3歳から接種開始になりますが、生後6か月からの接種が可能ですので、早期の接種をご希望の場合はご相談ください。
二種混合(DT)ワクチン、三種混合(DPT)ワクチン
二種混合ワクチンは五種混合ワクチンの内、ジフテリア、破傷風の二種類を含んだワクチンです。
二種混合ワクチンには百日咳は含まれていませんが、百日咳の抗体価も就学前に低下により、小学校入学後の百日咳の患者さんが増えています。
百日咳の予防のため、就学前にMRワクチンの2期に合わせて三種混合ワクチンの接種が推奨されております。
また二種混合ワクチンの代わりに三種混合ワクチンの接種も可能です。
どちらも現在は任意接種となるため、接種をご希望される場合はご相談ください。
接種可能年齢・回数
二種混合ワクチン:11~12歳に1回
子宮頸がん(HPV)ワクチン
HPVワクチンは子宮頸がんの原因となるヒトパピローマウイルス(HPV)の感染を予防するワクチンです。
2013年に定期接種となりましたが、接種後の症状などの調査のために積極的な勧奨接種が中止されていましたが、現在は積極的勧奨接種が再開されております。
HPVによる子宮頸がんを予防するために性的接触の経験前のワクチン接種が推奨されております。
ムンプス(おたふく/流行性耳下腺炎)ワクチン
おたふくは2~3週間の潜伏期の後に両側、または片側の耳の下が腫れる病気です。
感染しても症状が出現しない方も30%前後いると言われていますが、無菌性髄膜炎、精巣炎・卵巣炎、難聴などの合併症を起こすこともあります。
特に難聴は頻度こそ少ないですが、聴力の改善が難しい合併症となります。
現在は任意接種となりますが、多くの合併症を引き起こすことがあるためワクチンを接種しましょう。
1歳で1回、1回目の接種後2~6年経ったら2回目の接種をします。
どちらもMRワクチンと同時に接種されることをお勧めします。
インフルエンザワクチン
インフルエンザは冬に流行する感染症で、突然の高熱、だるさ、のどの痛み、関節痛などがみられます。
1週間程度で症状は改善することが多いですが、時に肺炎や脳症などの重篤な症状を引き起こすことがあります。
インフルエンザワクチンは発症予防効果としては他のワクチンと比べ高くありませんが、重症化を予防効果があるため接種することをおすすめします。
毎年少しずつ流行する型が変わるため、毎年ワクチンを作り変えて接種する必要があります。
生後6か月以上13歳未満は2~4週を空けて2回接種、13歳以上は通常1回接種となります。
接種後2週以降に免疫が誘導されるため、流行前に少し余裕をもって接種しましょう。
2024年から2~18歳で接種できる鼻にスプレーする生ワクチンも発売されました。